コロナ禍の影響は、運賃や物価に反映されて行くのは、これからの流れなのだと思う。
ただ公共交通機関は、そうした中でもなかなか運賃に反映できないコトが多い業態だと思うのですが、公共交通機関にも、そうした動きが出て来るのかな…
東急、運賃値上げを申請!
首都圏大手私鉄の東急電鉄が、2022年1月7日に、2023年3月の運賃改定を国土交通省に申請を行ったコトを発表しました。
首都圏の鉄道事業者としては、コロナ禍後に、運賃の値上げを軸とする改定は、東急が初めての申請。
改定率は、約12.9%で初乗り運賃は10円程度の値上げ。
但し、通学定期については、“家計負担に配慮”するとして据え置きに。
またこどもの国線も通常運賃・定期運賃ともに据え置きでの申請になっています。
具体的には、以下の通り。
対象路線 | 普通運賃 | 定期|通勤 | 定期|通学 |
東横線 | 初乗り… 例|渋谷~横浜間 309円(IC) | 12.9%と同程度 | 現行据え置き
|
世田谷線 | 147円→160円(IC) | 12.9%と同程度 | |
こどもの国線 | 現行据え置き | 現行据え置き |
渋谷~横浜間だと、IC運賃で現行だと272円が309円になり、300円台に到達する改定と言うコトになり、なかなかのインパクトと言える感じですね。
今の運賃体系が、大手私鉄の中でもかなり安く頑張っているだけに、ついそう思えてしまう自分がいます…
設備投資とコロナ禍での需要減退が理由
運賃の改定理由としては、まずは設備投資が大きく膨らんでいると言う点。
ホームドアの整備・車両防犯カメラ設置・バリアフリールートの2ルート目の実施・構内トイレの多機能化などを進めて来たのに加え、田園都市線へ新車両を導入、大井町線急行列車の7両編成化と言った設備投資を継続して行っており、投資額は関東の大手民鉄7社の平均額を大きく上回ると言うのが1点。
さらに今後も目黒線の8両編成化に加え、東急新横浜線の開業もありますしね。

そして何よりもコロナ禍に需要減退が大きい。
2020年度は165億円の営業赤字を計上(2019年度の営業利益は220億円)。
2021年11月の旅客収入は、2019年度同月比で運賃収入は定期外が10.6%の減まで戻しているが、定期収入は31.5%の減で、関東大手の私鉄としては最大の減収率が続いている状態。
特に東急は、ブルーワーカーが少なく、ホワイトワーカー層が沿線に多いのでしょうね。テレワークでの働き方が進んでいる状況で、そうした需要が戻ってないと言う感じなのでしょう。
利益はトントンになりつつあるけれど、値上げするの?
ただ…
2020年度は確かに大きな赤字額を計上していますが、2019年度の営業利益よりも低い額。
つまりは元に戻れば1年で回復できるような額。
そして直近の2021年度第2四半期は、営業利益で249億円。四半期純利益で241億円と黒字転換しています。
もちろん、黒字転換したのは、不動産セグメントと言うのが大きく、営業利益のほとんどをこのセグメントで稼いでいる状態ですが、交通セグメントも利益ベースでは大きく改善している状態。
通期での当期純利益も100億円の黒字を予定している状態。
交通セグメントも損益的にはトントンに迫っている状態だし、引き続き、大きな赤字を抱えそうなセグメントは、ホテル・リゾートのみ。
それでいて値上げ申請と言うのは、どうなんだろう?と言う感じはしてしまうけれど。

理由として掲げられている設備投資にしても、既に東急は東横線・田園都市線・大井町線では全駅にホームドアやセンサー付きホーム柵を設置済み。
これは大手私鉄としても初の快挙であり、それまでに巨額の費用を費やして来たのは間違いがナイ。
で、他にも車内防犯カメラも既に100%設置しているし、駅構内多機能トイレの整備率も100%。
確かに今後も新車両の導入などが控えているけれど、既に全駅での整備が進んでいるモノも多い東急なので、それを理由に値上げと言うのは、ちょっと安易な感じがしなくもないけれど。
寧ろ、渋谷の再開発を本格化させるために、基盤強化のための値上げと思ってしまうぐらいだけれど。
でも、コロナ禍で厳しい状況なのは事実。
ホームドアも整備は進んでいるけれど、更新・ランニングコストも乗って来ますしね。
これ以上、コロナの影響が長引けば、一民間企業としては、限界に近付く公共交通機関も増えて行くだろうとは思う。
東急は今まで運賃が、かなり抑えられていましたしね。
値上げと言うのは、その解決法の1つなのは確かではあるのでしょうが、どれだけ社会が許容できるのか…と言う気もしますが。
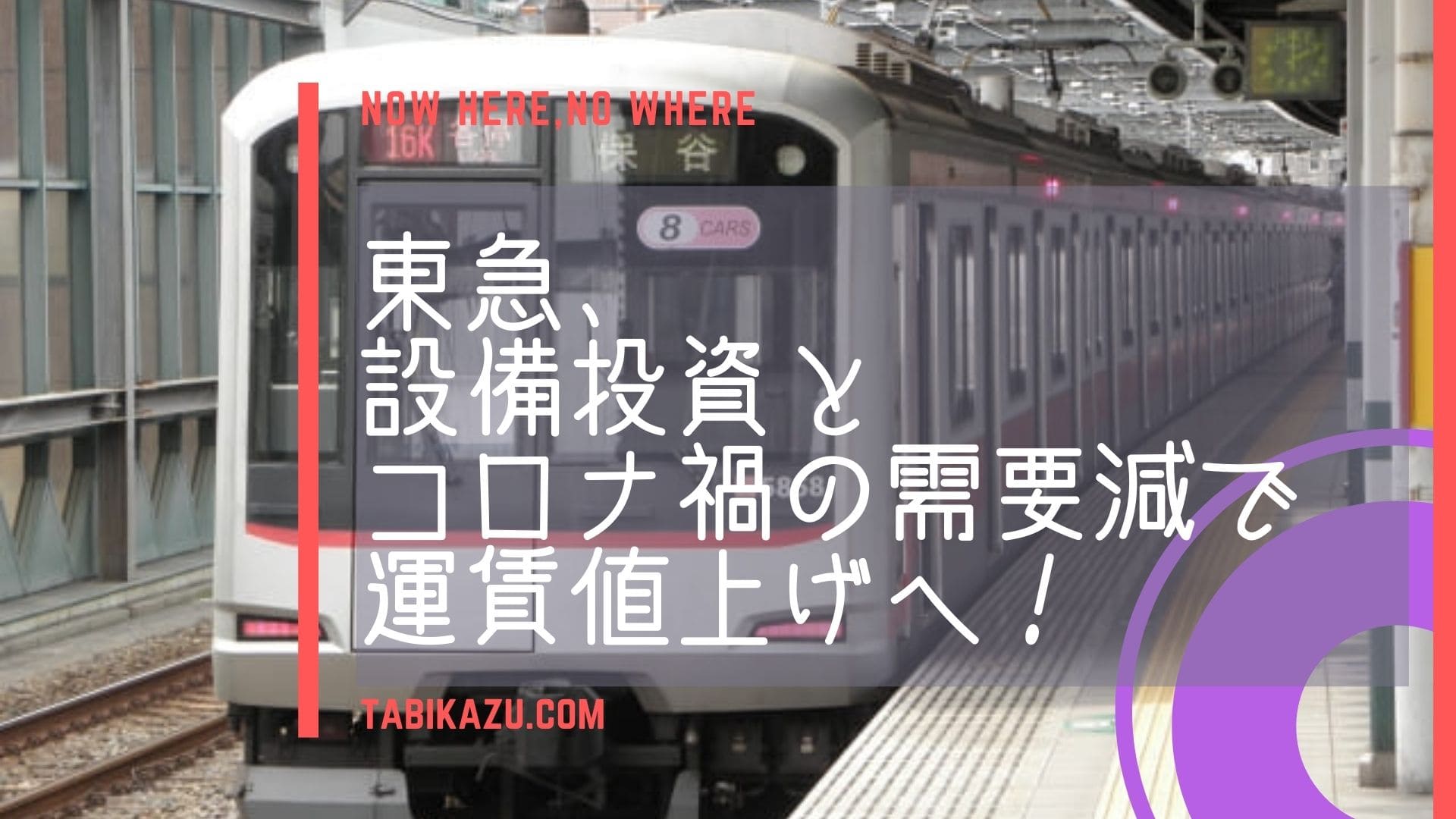


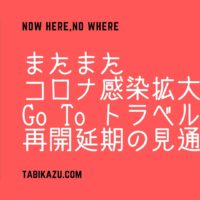
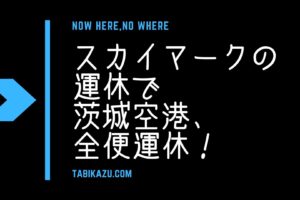


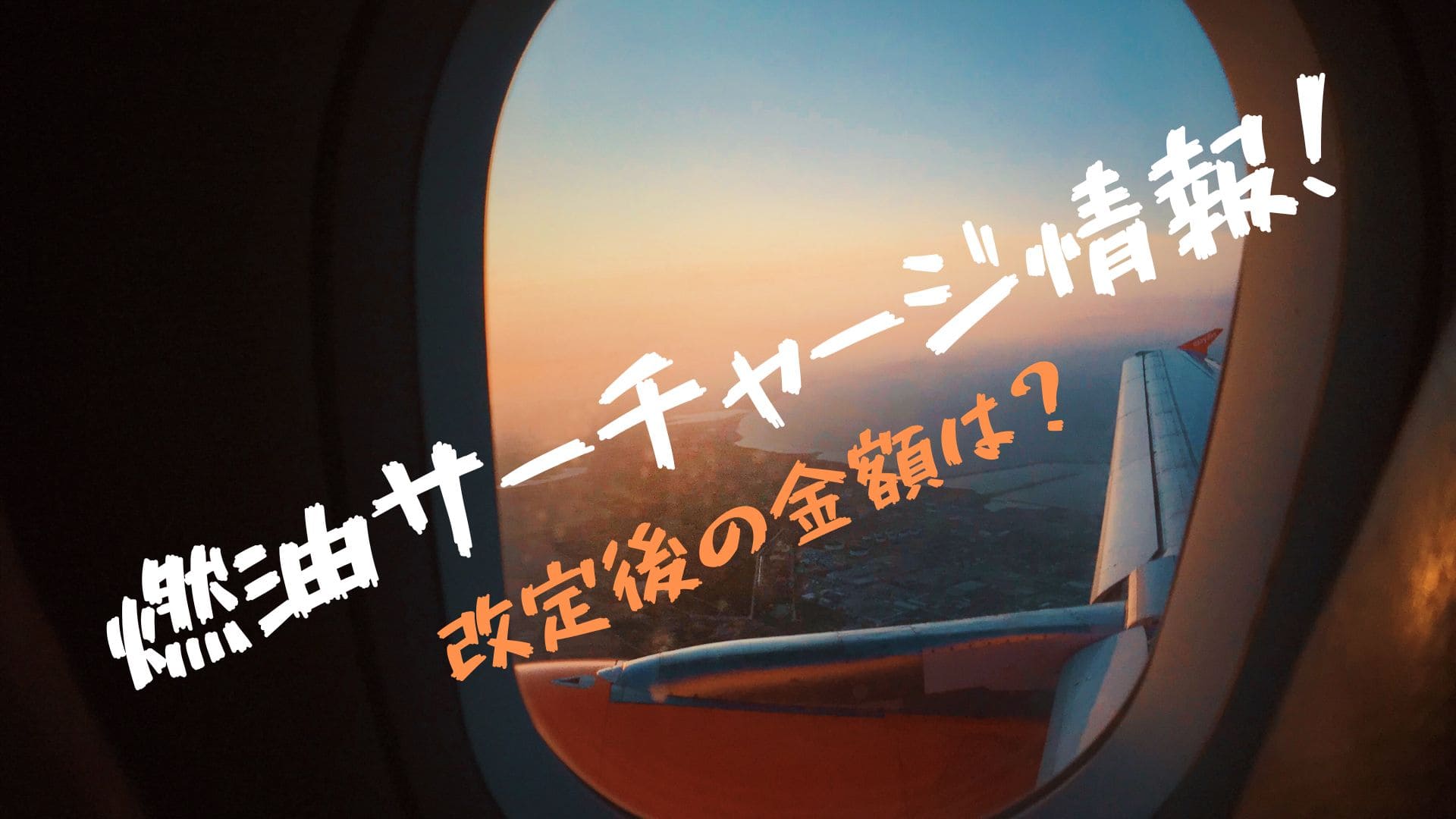






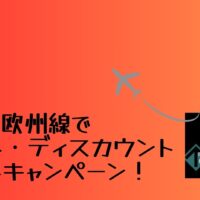
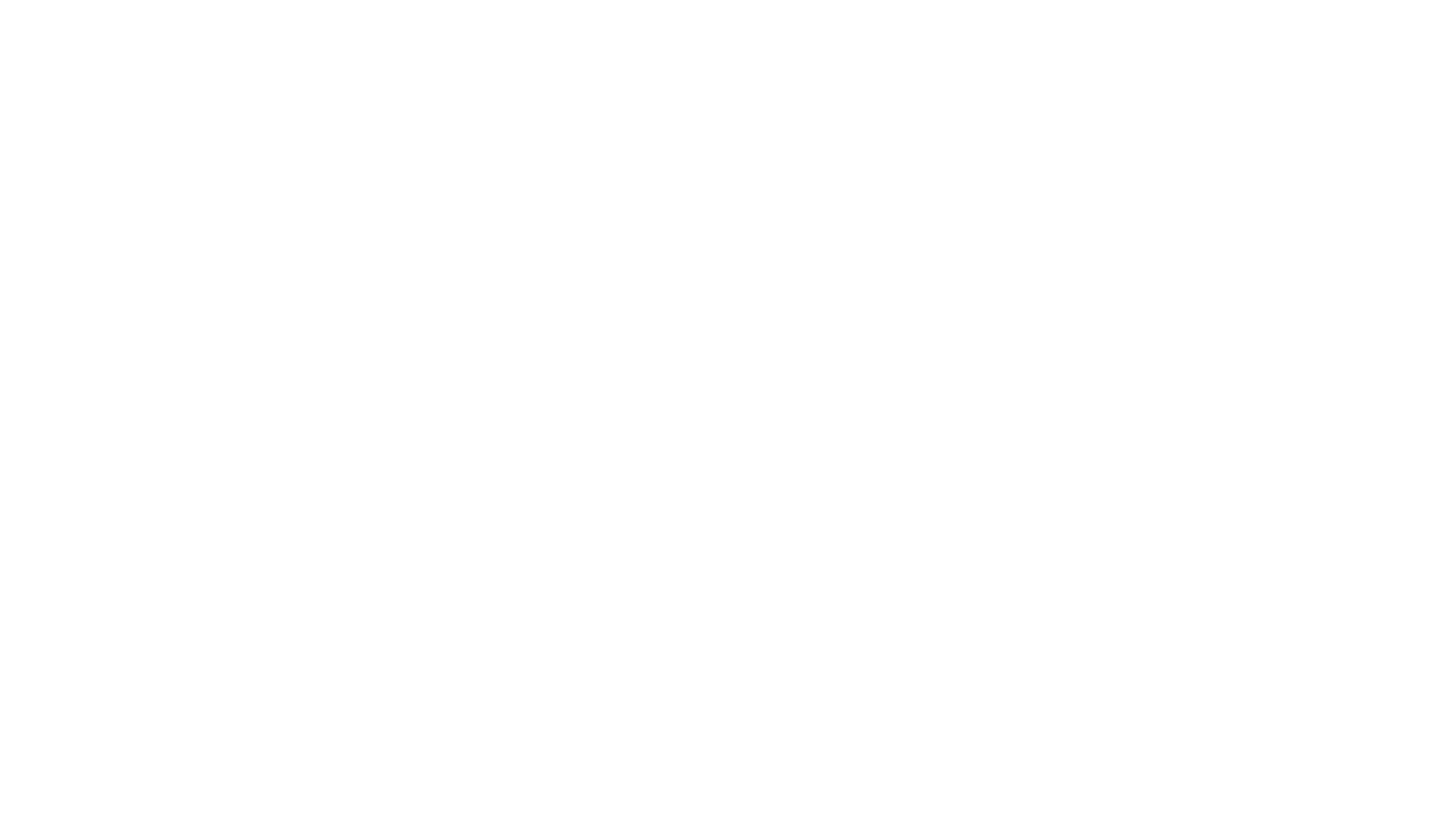

コメントを残す