『転がる香港に苔は生えない』
著:星野 博美
刊:文春文庫
星野博美と言う著者を知ったのは、第1作の『謝々!チャイニーズ』だった。
改革開放に沸く鄧小平時代の中国・ベトナム国境の東興から寧波までを北上したバス旅を1つの作品にしたモノで、そこそこ本屋の棚でも目にしたので、ある程度は売れたんだと思う作品(と言うか、まだ旅行作品と言うのもそんなに多くない時代でしたしね)。
だが、実際にボクが本を買ったのは、2作目のこの本だった。
とても分厚い本。
当時、まだ学生だった身にしては、本の厚みの分だけ値段も高く、気軽に買えなかったけれども、それでも惹き込まれる本だった。
香港返還を知っている世代は、どれだけいるのだろう…
1997年7月1日。
香港返還を中心に据え、2年間の香港での生活が描かれた作品。
もう“香港がイギリス領だった”と言うコトを意識する人も少なくなっただろうし、そもそもイギリス領だったコトすら知らない世代が旅をする様にもなっている。
でも、“香港が香港である理由”は、中国本土領ではなかった時代があったからこそだと思う。

だけれども、少しずつ時代は移り変わる。
最早、“香港が香港だった”と過去形にするのが正しくなる日も近いのかも知れない。
いや、実際には、もうそう言う時代になっているのかも知れない。
だけれど、その“香港が香港だった”1番の時代。
それがこの2年間なのだろう。
生活する人の視線、その背景。
そして日々と人との繋がり方。
どんな香港の本を読むよりも、当時の香港が分かる。
それは、ガイドブックには描かれない貴重な体験談。
そんな1冊だと思う。
調景嶺、九龍城塞…
あの頃にあったモノ。
今となっては見るコトが出来ないモノ。
確かにそう言った記述も多いのだけれど、つい、その当時の香港に行きたかったなぁ…と言う感じに思うのは、本書のリアルさと香港の激動さなのだろうか。

変わる続ける街が、止まってしまうかも知れない。
何かに飲み込まれるかも知れないと言う漠然としたモノ。
香港の持つ歴史が過去に執着させ、未来への不安を呼ぶ。
そんな時代の短い日記を何本も読んでいる様な感じ。
ただテンポが良くて、1冊はとても分厚い本だけれども、あっと言う間に読めてしまう。
啓徳空港に降り立ってみたかった。
実際に街中から降りて来る飛行機を見上げてみたかった。
九龍要塞を訪れてみたかった。
でも、著者より一世代若かったボクは、それが出来なかった。
時代が変わる瞬間
そして返還。
“時代が変わる”と言う瞬間に立ち会える機会と言うのは、人生においてもそうあるモノじゃないけれど、香港に住む人々にとっては、香港返還と言うのは、間違いなく、“時代が変わる”瞬間だった様に思う。
その後の香港は、やっぱり少しずつ本土のチカラが増している様にも思う。
元から香港に住んでいた人だけでなく、香港返還以後に本土から移り住んで来た人も多いだろうし。
本土自体も、経済的に発展を見せているし、狭い香港と広い本土との力関係は、変わって来ている。
香港が必要な本土ではなく、本土が必要な香港。
もうそんな時代になっていると思う。
でも、だからこそ、後日談ではないけれど、“その後の香港”と言うのを読んでみたいと思う。
『香港のどんなところが好きのかと尋ねた時、彼はこういった。
「ここは最低だ。でも俺にはここが似合ってる」
そのセリフを聞いた時、自分にはそんな愛に満ちたセリフをいえるだろうかと思った。』
ボクが香港を好きなのも、もしかしたらそんな部分にあるのかも。
気高くお高くアフタヌーンティーを楽しむ様なスポットもあるけれど、それだけではなく。
観光客が歩くエリアと、現地の生活圏が近く、ちょっとした路地の暗闇の先に、何かがある様な、そんな気持ちになる香港。
この本は、ボクの中では、沢木耕太郎の『深夜特急〈1〉香港・マカオ (新潮文庫)』と並んで、香港の原点になる風景を持つ1冊なんだと思う。















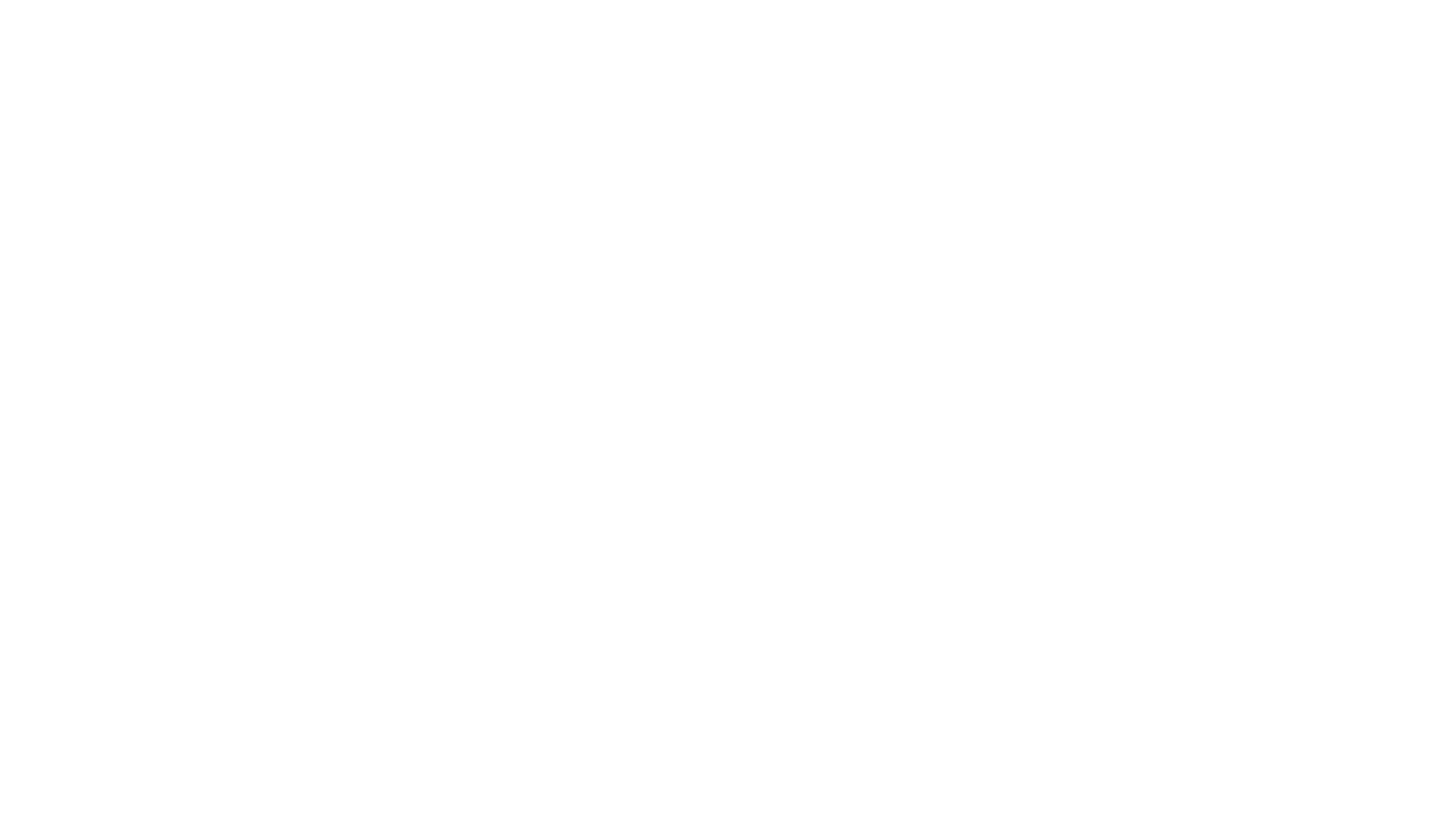

コメントを残す