西九州新幹線、開業日は9月23日で決定!
JR九州は、武雄温泉~長崎間で建設中の「西九州新幹線」の開業日を、2022年9月23日に決定したコトを発表しました。
「西九州新幹線」は、博多~長崎間を結ぶ整備新幹線の九州新幹線西九州ルートとして、1973年に計画路線に。
整備方式が当初は、博多~武雄温泉間を在来線で走行し、武雄温泉~長崎間は、構造物は新幹線規格で建設するが、軌間は在来線と同じと言うスーパー特急方式を採用するとしていたのですが、2012年に政府が武雄温泉~長崎間を通常のフル規格で整備する方針に転換。
2008年に武雄温泉~諫早間が着工した後、諫早~長崎間も着工。
博多~武雄温泉間は在来線(狭軌)で、武雄温泉~長崎間は新幹線(広軌)を走るフリーゲージトレインで直通運転する方針が示され、2014年から実際に試験が開始されたが、技術的な問題をクリアできず、採算面でも厳しくなるコトから、2016年に武雄温泉~長崎間を先行開業し、当面は武雄温泉駅で新幹線と在来線との対面乗換を行なうコトが決定し、2017年にフリーゲージトレインの開発断念が発表に。

紆余曲折はまだまだ続き、九州新幹線との分岐になる新鳥栖と武雄温泉間を政府がフル規格で整備する方向性を見せたため、在来線を活かせなくなる佐賀県が反発。
その為、現時点でも新鳥栖~武雄温泉間の整備方式を巡り、幅広い協議が進められている状態で、2月10日開催された協議でも目立った成果がなかったほどに、佐賀県と国との方針の違いと言うのが、際立ったままである。
こうした中で、今回、9月に西九州新幹線の武雄温泉~長崎間が先行開業するコトになる。
肥前山口~諫早間は、上下分離方式を採用!
途中の停車駅は、嬉野温泉・新大村・諫早駅の3駅。
嬉野温泉駅のみ新幹線単独駅で、新大村で大村線と、諫早で長崎本線・大村線・島原鉄道と乗り換えが出来る。
並行在来線の長崎本線は、肥前山口~諫早間については、佐賀・長崎県が鉄道施設を保有し、JR九州が開業から23年間は運営を行なう上下分離方式を採用(肥前山口駅は、西九州新幹線開業と共に、江北駅へと改称予定)。
諫早~長崎間は、経営分離もされず、JR九州が引き続き、保有し運営するコトに。

この部分も当初は、肥前鹿島~諫早間は、第三セクター鉄道に移行すると言う形を想定していたが、鹿島市・江北町が利便性の大幅な低下と将来的に並行在来線区間の利用が低迷すると廃線になる可能性に懸念を示し、当初、経営分離に計画に反対の意見を出すなど、混乱した経緯がある。
まだまだ佐賀県内の整備方式が決まらないなど、混乱している最中だけれども、この路線ほど右往左往している路線も、近年では珍しいように思う。
ってか、“先行開業”ではあるけれど、その後の道筋も立っていない状況ですしね。
なぜフル規格が採用されたのか…
新幹線。
それができれば、確かに大きい。
フル規格での建設ならば、その恩恵はさらに大きくなるのは確か。
ただそこまで観光需要が高くない自治体は、通過されるだけだし、そもそも日常で利用する路線の存廃に直結する話。
もっと慎重に話を進めるべきであったように思うし、先行開業は、完全に政府(と言うか自民党の横槍)に落ち度があるように思う。
どうしてフル規格なのか。
それが今一つ、しっかりと提示されていないようにも思う。
あくまでも、フル規格ありきの試算であり、そりゃ、フル規格なら便利にはなるけれど、不便になる・費用対効果と言う部分の試算は、今一つと言う感じ。
長崎県には意味があるけれど、佐賀県からすれば、今でも博多までは速度の速い特急で不便はしないのに、費用だけは膨大な訳ですし。
そう考えると、やはり工事期間は長めだし、そこまで収支改善効果が高いとは言えないけれど、ミニ新幹線方式の複線三線軌がベストな選択だったように思う。
試算だと、新大阪~長崎で約3時間38分。
この時間ならば、飛行機と比べても対抗できるし、所詮、フル規格で建設しても約3時間15分で、3時間は切れない想定な訳なのだから。
ただ先行開業はもう決まってしまった訳だから、これからはどれだけこの開業に意味を持たせられるか…と言うコトになりますね。
あまりにもゴタゴタしていて、イメージの良い新幹線ルートではないけれども、それを跳ね返す企画が出てくるとイイですのになぁ…と。
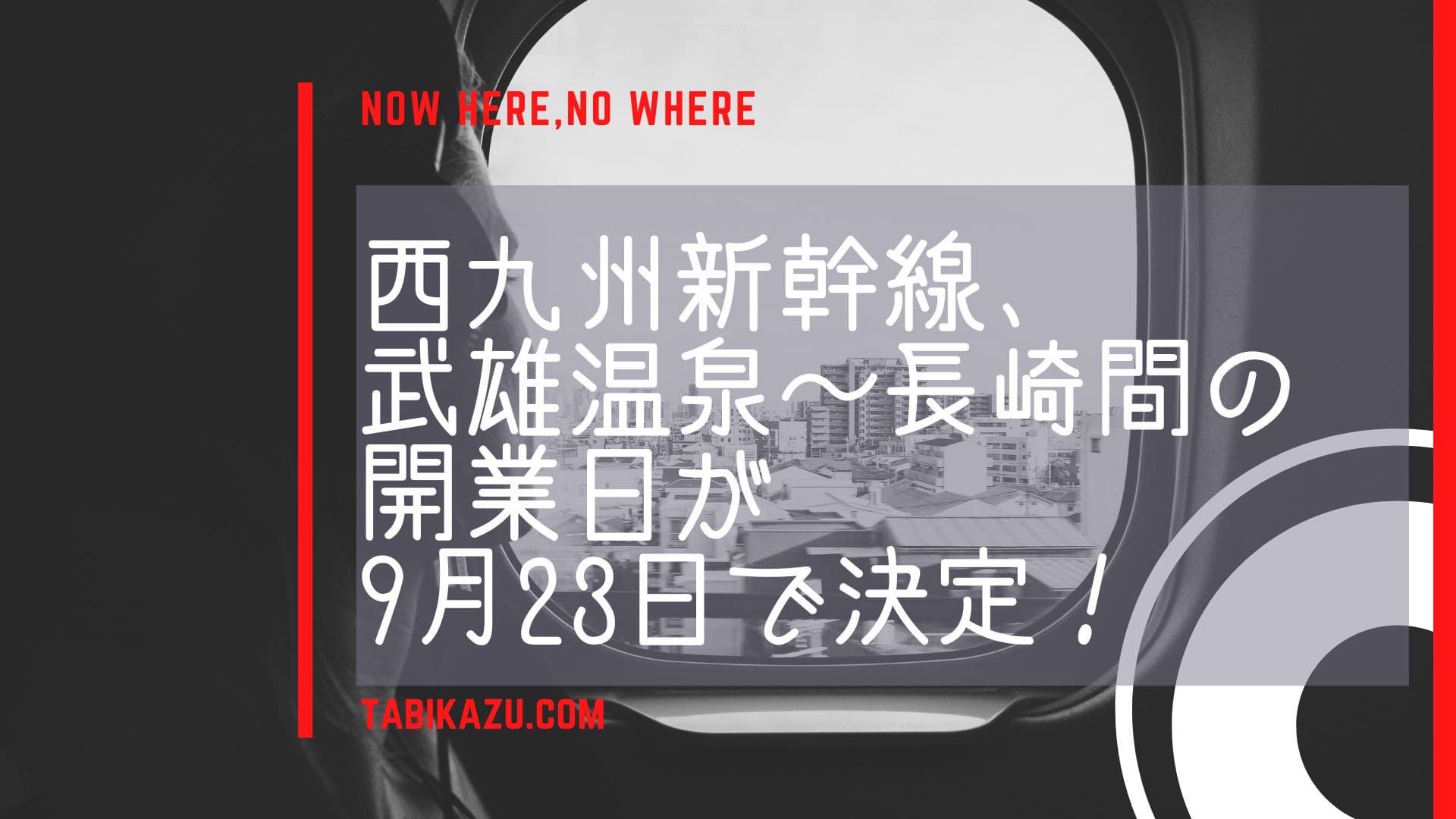

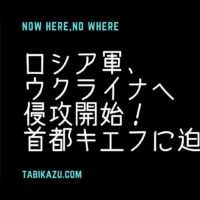
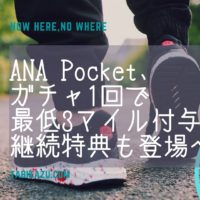

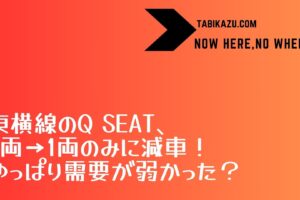


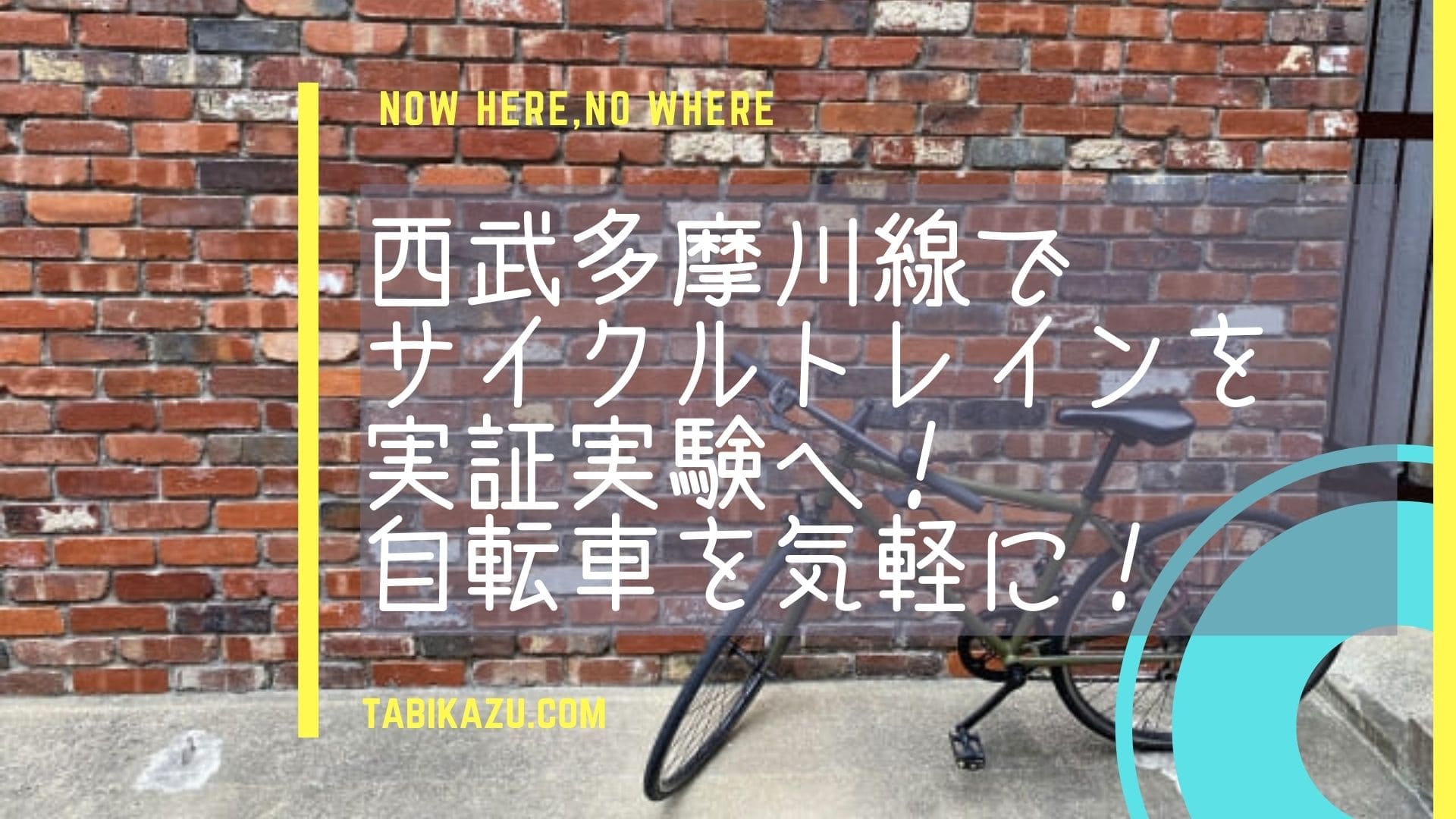





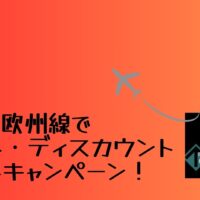
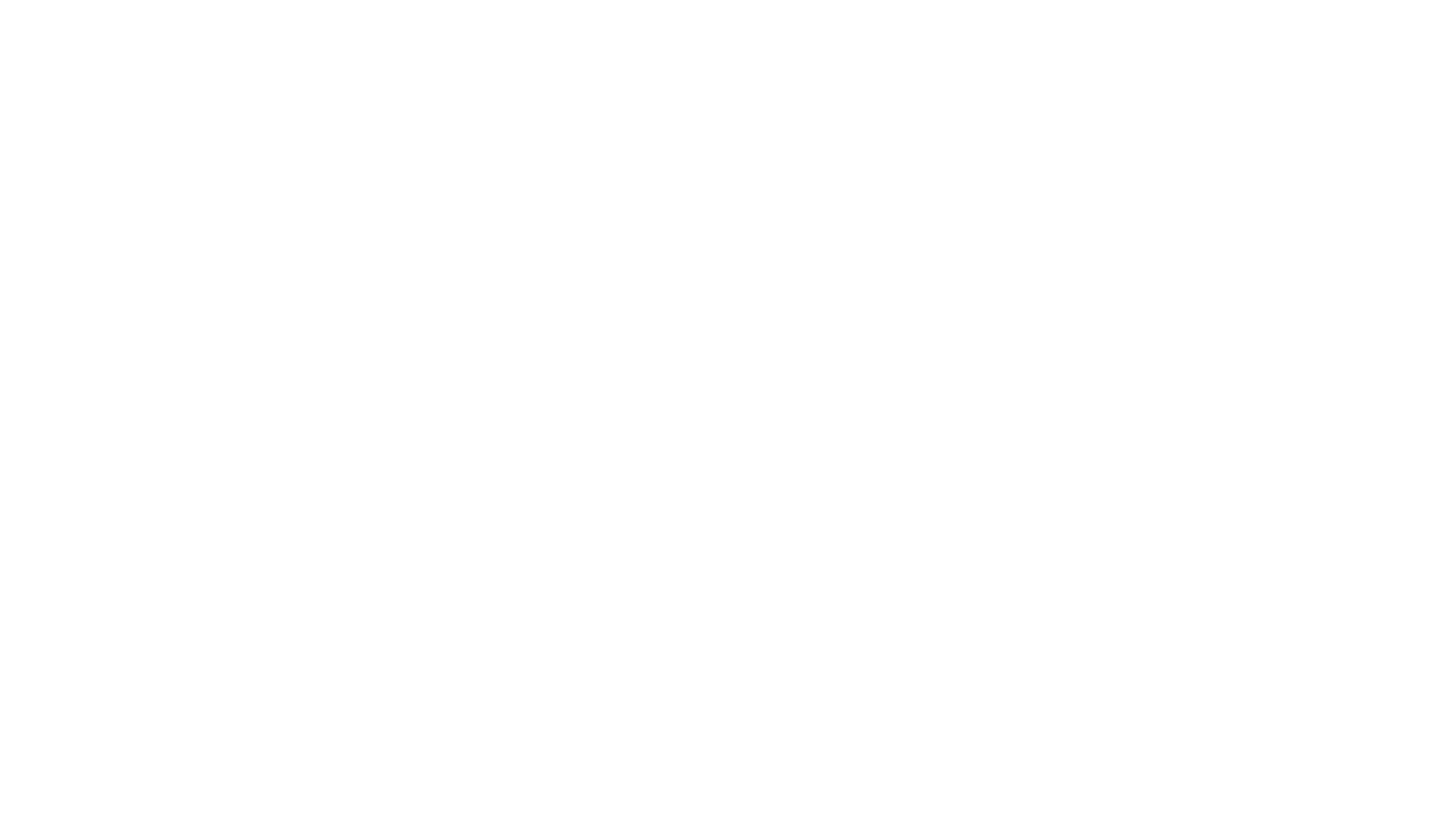

コメントを残す