『月と金のシャングリラ』
著:蔵西
刊:イーストプレス
中国軍が近付くチベットが舞台
チベットと言っても、インドのラダックなどのチベット文化圏での話である『流転のテルマ』をデビュー作に持つ著者(『流転のテルマ』の情報は、こちら)。
最終巻がなぜか電子書籍のみと言う残念な結果だった『流転のテルマ』ですが、本作は2巻完結で手軽に読めるし、2巻目も先日、発売済みで安心(そう言えば、このブログで、新刊を取り上げるのって、なぜかマンガばかりなんだよなぁ…)。
さて今作は、チベット本土が舞台。
物語の時代は、1940年代からのチベット現代史の中でも、ひときわ“激動”だったと言えるであろう中華人民共和国によるチベット侵攻の頃合い。
僧院に置き去りになった主人公のダワと、その僧院で出会った少年僧のドルジェを中心とした物語の展開で、1巻目は、時代の流れを感じる展開は、そう多くはなく、僧院・仏像・勤行・僧の生活スタイル…と言った細かい描写が、びっしりと。
線が力強いのに、細部の緻密さが何ともミスマッチ(誉め言葉です)。

ただ個人的には、前作でも思ったけれども、引きの構図の風景描写になると、ちょっと“グシャッ”とした感じを受けるので、この辺りは好き嫌いが分かれるのかも。
強いて言うならば、“魚眼レンズ”を通してみた風景を描いている…みたいに思える。
あくまでもチベットの奥深さ・山の高さなどを表したいと言う表現としてこう言う描き方になっているのかどうかは、不明ですが。
でも、それよりも装束・仏具に至るまで描き込みや、人物の表情(特に目力)が、何ともステキです。
時代のうねりの中の人のチカラ
後編にあたる2巻に入って来ると、一気に物語が動いていきます。
山奥の僧院から、聖地・ラサへ。
物語の軸の1つとして、BL展開になる訳ですが、“僧・愛・家族・時代…”と、幾つかの軸が絡み合っていくような状態。
抗えない時代の大きなうねりの中に、チベットが巻き込まれて行く。
それは、チベットでは現在にまで続く時間の流れ。
こうしたうねりの中で、被害を受けるのは、いつだって・どこだって庶民な訳だけれども、そう言った部分もちょっと描かれています。
その中に、祈りのチカラがあるのか、それとも祈りのチカラは無力なのか。
今でも分からないけれど、祈る場所があると言う人は、それだけで幸せのようにも思う。
何かにすがれる場所があると言う意味で。
個人的には、2巻の展開、早くて好きです。
内容的には別に軽くないんだけれど、テンポが早いので読みやすい感じ。
テンポが良くて、それでいて主人公のココロの移り変わりがしっかりと描かれていて。
自由にラサに行ける日…
チベット。
民族構成が変わって来て、時代も流れ、ラサを中心としたチベットにも行きやすくなり、どんどんと変わって行っているのだろう。
チベットが中国に。
それが、どこまで進んでいるのか。
そして、いつになったら自由に旅行ができるようになるのか…
いや、もうボクが生きている間に、そんな時が来るのだろうか。

21世紀になって、IT化も進んで、どんどん旅がし易く、便利になって行くのだと思っていたけれど、どんどん行けない・行きにくくなる場所が増えて行くのは、どう言うコトなのやら。
でも、そんな時代のチベットの作品も、ぜひ読んでみたい。
なんだか、そう言う気持ちになったけれど、きっと読んだら焦燥感に駆られるだけなんだろうな。
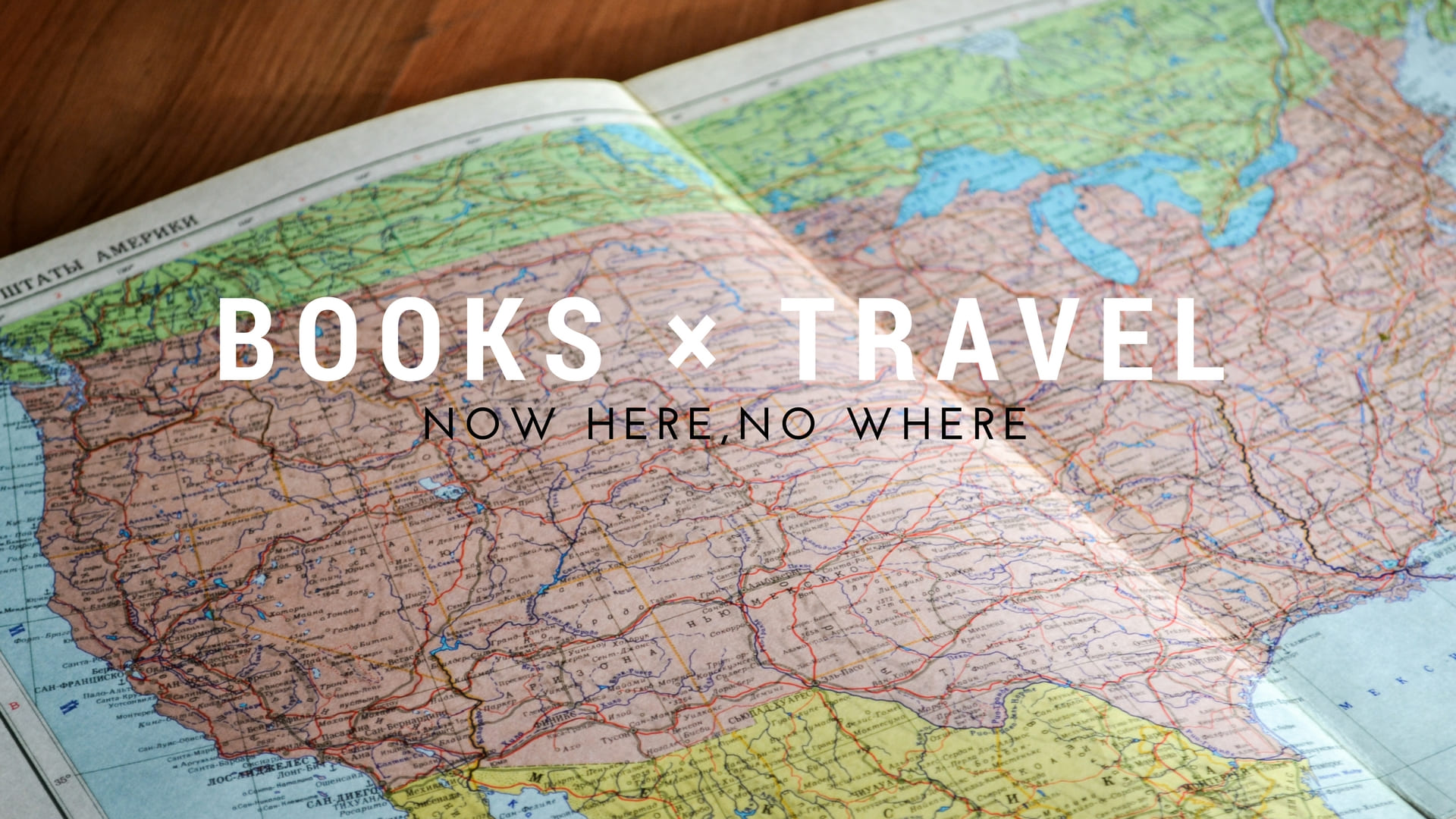


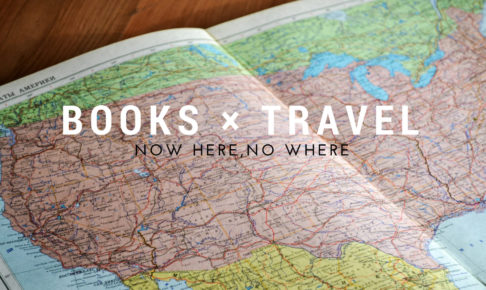
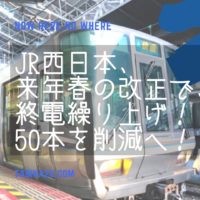






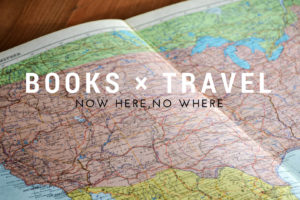

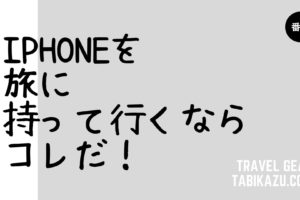


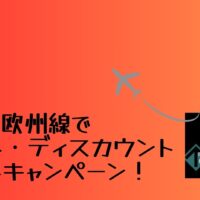
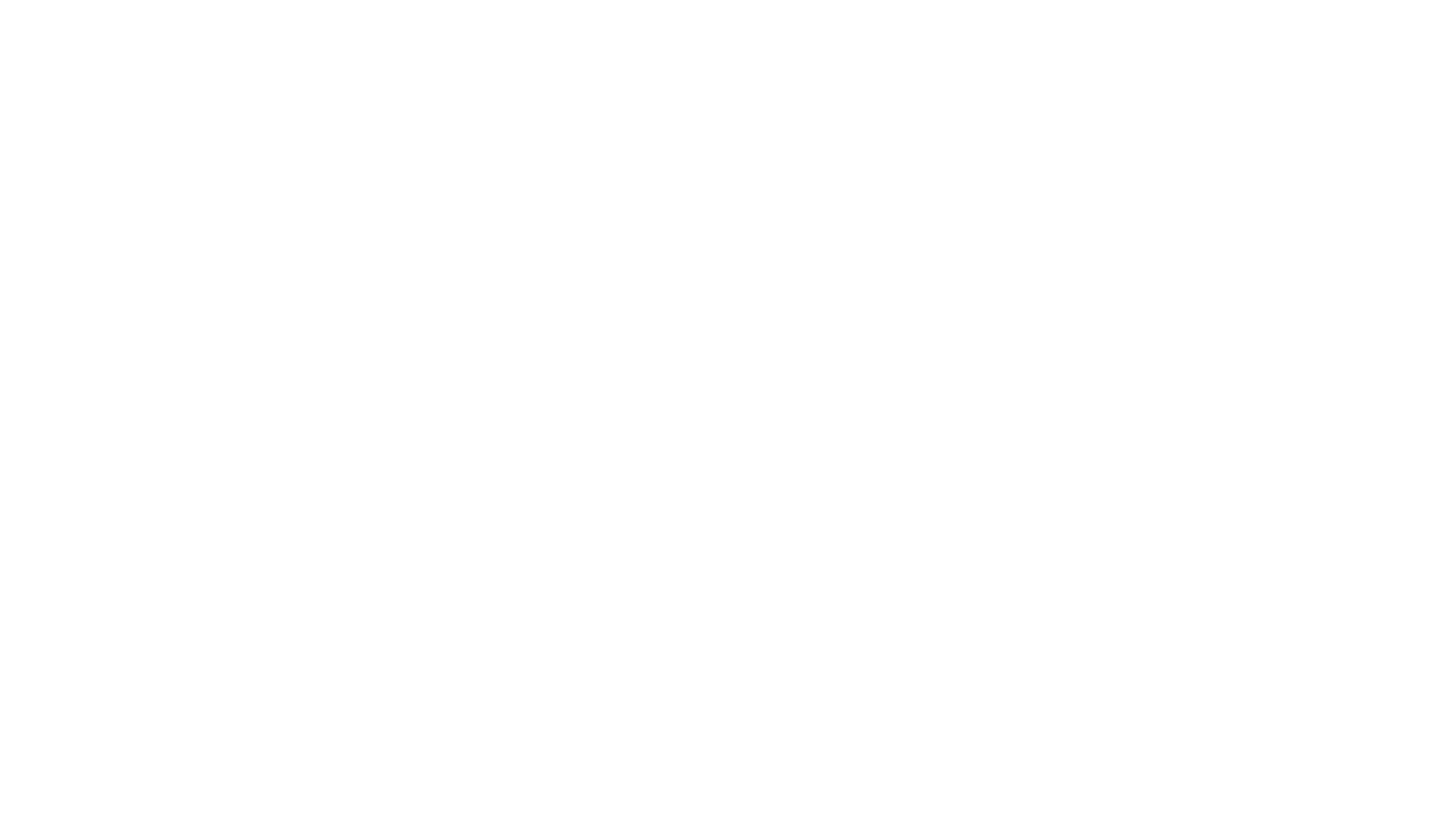

コメントを残す