車いす利用者の搭乗がスムーズに!
車いす利用者が、スムーズに航空機に搭乗出来る様に、国土交通省は、2018年10月から航空会社に支援設備の完備を義務付ける方針を固めたコトが明らかに。
この話の経緯は、去年、バニラエアの奄美大島線で、車いすの男性が、一旦、搭乗を断られたり、腕の力でタラップを上がらなければならなくなったと言う事態が発生したと言うコトがきっかけになっている。
バニラエアとしては、奄美空港には階段式のタラップがあるコトを理由に、
「歩けない人は搭乗出来ない」
と搭乗カウンターで搭乗を拒否。
ただ同行者がいたコトもあり、「同行者に手助けをして貰う」コトで搭乗し、同行者に担いで貰ってタラップを降りた。
逆に帰路は、バニラエアが委託をしていた空港職員に規則違反だと止められ、車いすを降り、腕を使って、自力で17段のタラップを上がるコトを余儀なくされた。

こうした一連の対応から、国交省が対応を検討。
車いす利用者の搭乗に必要な設備や器具を備える様に、各社に義務付けるコトにしたと言う話。
具体的にイメージとされているのは、
・スロープ付きの搭乗ブリッジ
・リフト
・車いすで昇降できるリフター
などが考えられている模様。
事前に連絡をするコトで、何が変わるか?
確かに、航空業界のバリアフリー化は、進んでいるとはいいがたい。
それは車いす利用者だけでなく、それ以外の障害を持つ人に対しても。
でも、そもそも奄美大島でバニラエアが問題になったのは、
・奄美大島の空港には当時、設備がなかった
・車いす利用者の搭乗に際しては、事前に連絡と承認が必要だったのを怠った
と言う2点ではなかろうか…とも思う。

世間一般ではまだまだ事前に車いす利用者が連絡をする必要があると言う施設は多い。
今回のバニラエアの様に、それがなかったから利用を断ると言うケースも少ないだろうが、やっぱりスムーズな利用の為には、連絡をしておくべきだと思う。
バニラエアへの搭乗の場合は、それを意図してしなかった節があった。
車いす生活になってから世界158カ国を訪れた人なのだけれども、「その時、気づかなかった」とおっしゃられている。
158ヶ国も行っていて、そんなコト、あるかな…と。
まぁ、海外だと車いすの利用であったとしても、問題ない航空会社も多いみたいだけれど。
そして、例え、事前に連絡をしていても、バニラエアは乗せなかった訳で、それが何か変わるのか?と言われたら、「変わらなかった」と言えてしまうのかも知れないが…
自分では歩けないから同行者に車いすを担いで貰おうとしたらダメと言われ、自力で上がろうとしたらそれもダメと。こちらはどうやったら乗れるか知りたいし、それによって提案も出来る訳ですよ。「いつもやっていることだから大丈夫です」とかも言えるし、最後は自己責任でと言う覚悟もある。
https://www.huffingtonpost.jp/2017/07/29/hidetou-kijima_n_17629944.htmlより
とある。
「いつもやっていることだから大丈夫です」と言われるのが、一番、困る気がするけれど。
そして、それならば尚更、最初に連絡をして、そこで提案をしていれば、こんなに大きな騒ぎにはならなかった可能性だってあるのに…と。
バリアフリーな旅に向けて

何だか後味が悪い出来事だったなぁ…とは思っていたのですが、こうしてコトが動いた。
問題を提起していたからこそ、コトが動いたのは事実。
そう言う意味では、意味があった訳だ。
色々と賛否はあった出来事だったけれども、元からのルールを守った上で、これからも問題は提起して貰いたいとも思う。
やっぱり車いすの利用者だからこそ、気が付く不便さと言うのもある訳で、その意見を挙げて行くと言うのは、これからも必要なコトだから。
また、車いす利用者以外の障害を持った方も、搭乗に関して、難関があるケースもあるだろう。
そうした方々へもバリアフリーの実現が進めばいいのですけれどね。
でも、それよりも前に、バリアフリー社会の実現に向けて、もっと社会全般が協力的になる必要があるのかも知れないけれど。
そもそも国交省的には、“東京オリンピック”“東京パラリンピック”の開催があると言うのを踏まえたバリアフリーの促進と言う考えなのだろうけれど、こうしたイベントがないと共生出来る社会化にならないのであれば、まだまだ共生出来る社会にはならないと言える様に思うのだが。







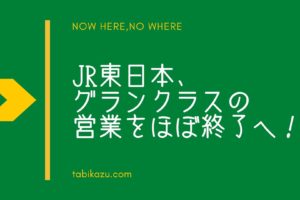





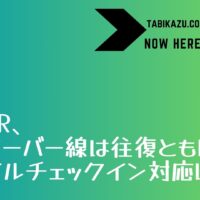


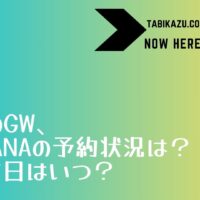
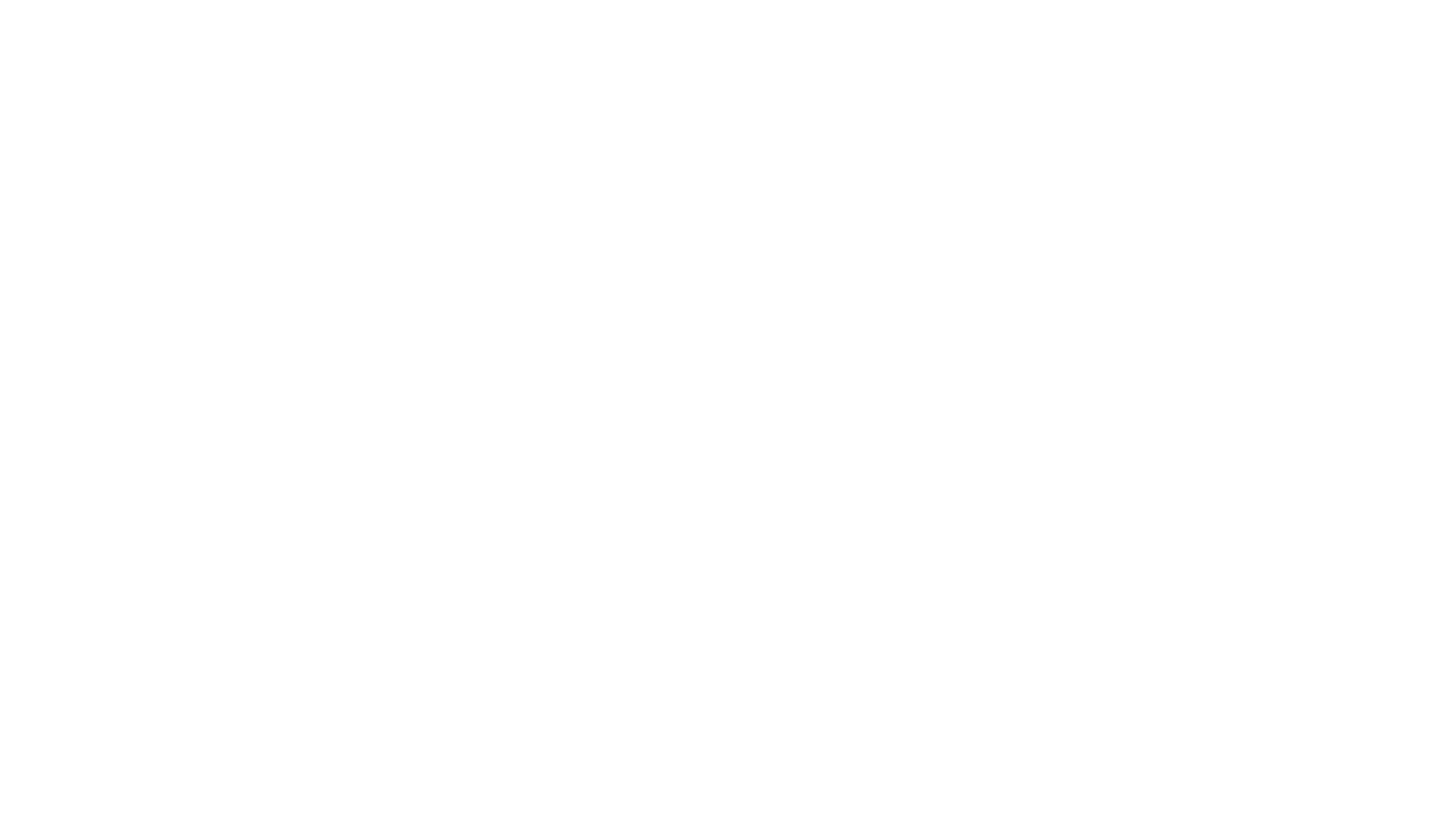

コメントを残す