先日の関東に降った大雪。
ニュースで駅前にタクシーを待つ行列が出来ていたのを見ましたが、どう考えても、“こんな大雪の日にタクシーなんて動くのかな…”と言う点。
どれぐらい待っていれば、タクシー、来るんだろ、あれだけの行列で…
まぁ、帰る手段が限られてしまう場合、“雪だから…”と言っても、待たざるを得ないんでしょうし、どうしようもないんでしょうけれど。
でも、待っている人で同じ方向の人を募って行けば、もっと早くに帰れるだろうに…とも。
こう言う場合のタクシーって、1台の車に大体1人しか乗らない訳で。
特にボクが住んでいる街は、関東でもかなりの郊外にある街だからか、それが顕著で、駅の出口は2ヶ所あるのですが、どちらもニュータウンに帰る人が大多数。
相乗りすれば、きっと列は半分になるのになぁ…と思う。
それは雪の日だけじゃなくて、年末の金曜日の終電後とかも同じ様な状態なんですが。
でも、そう言う時って、なかなか声が掛けにくいモノだから、上手くは行かないんでしょうけれど。
相乗りタクシーとは…
さて、そんな相乗りタクシー。
日本で合法化と聞かれると、そもそもが微妙。
まず、日本では「乗合」と言うコト自体が、微妙。
国交省による「乗合タクシー」の許認可を得ずに、不特定多数の乗客を1度に乗車させるのは、違法行為に当たる。
なので、タクシーの運転手などが同じ方向の人を募って、1台に乗せると違法になる(そもそもこの場合は、それぞれの乗客からそれぞれ運賃を徴収するので、全然、安くない)。
が、乗客の意思によって同乗する「相乗り」は乗合行為には該当しない為、合法になる(つまりは、乗客が単に“割り勘”をしたと言う考え方になるみたいです)。
タクシー業界を守る為。
何かあった場合の、法的な責任問題と言うのもあるのでしょうが、日本ではいわゆる「白タク」と言うのも、認められていませんし、何気にタクシーって、規制緩和の波があまり進んでいない業界と言えるのかも。
全てが全て、規制を緩和すると言うコトが正しいとは思えないけれども、革新的なサービスが導入されにくい業界の1つなのかも。
[amazonjs asin=”4478102600″ locale=”JP” title=”km(国際自動車)はなぜ大卒新卒タクシードライバーにこだわるのか――「人財育成」で業界を変える!”]タクシーの「相乗り」アプリがリリース
そんな合法的なタクシーの「相乗り」をサポートするアプリがJapan Taxiからリリースされました。
こちらは国交省が2018年3月11日まで実施する相乗りタクシーの実証実験だったりはしますが。
どう言うアプリかと言えば、
・アプリで乗る場所と行き先を指定する
・アプリが付近で同じ方向に移動したい他のユーザーを検索する
・双方が相乗り条件に合意すると、アプリが自動で近くのタクシーを手配
・支払はアカウント登録時に設定したクレジットカードから、事前に乗車距離に応じて振り分けられた相乗り料金が自動で引き落とし
つまりは、アプリが「同乗者の検索」「配車手配」「支払い」の3機能をこなしてくれると言うシロモノ。
何処までアプリのユーザーが広まるのかが勝負と言う所ではありますが、広まると、案外、便利になるかも…とは。

Free-Photos / Pixabay
パッと思いつくのは、終電後ですよね、やっぱり。
「終電を逃した」「途中駅まで終電が終わっていた」なんて時には、利用価値がある様な気がします。
特に、このアプリで「配車手配」まで行ってくれるので、上手くタイミングさえ合えば、駅で延々と待つ必要も薄くなる訳で、寒い冬の夜とかには何とも有り難いサービス。
また、終電後だけでなくとも、観光地とかでも、鉄道の駅から遠いのに、バスが不便と言う場所は結構多いので、利便性はあるように思える。
京都とかでも、観光シーズンになると大通りは大渋滞になるので、バスを使うとなかなか進まないコトがあるけれど、抜け道を走れるタクシーを利用すれば、ちょっとは楽に観光出来るようにもなるし(ならそもそも、1日貸切って回った方が安上がりかもしれないけれど)。
関東だと、箱根は駅からの交通手段がしっかりしているけれども、秩父って非常に微妙な感じだったりするし、温泉とかも何気にバスだと不便な所が多かったりしますよね。
このアプリが一般的になって、エリアも東京だけじゃなくて全国的に広がれば、そう言う場所を巡る時とかにも使えそうな予感が…
そもそも…
日本のタクシーって、高すぎるんですよね。
関東だと関西みたいに長距離割引もないから、余計にそう思っちゃったりも。
短距離だとちょっと安くなり始めてはいるけれども、根本的に、やっぱり高いと思うのは、海外のタクシーと比べちゃうからなんでしょうね。
収益が悪い・過当競争→値段が下がらない・規制が緩和されない
そう言う感じが、ついしてしまいます。
あくまでも実証実験なのかな…?
が…
さすが国交省。
何となく、お役所仕事です。
そもそもこの実証実験自体が、2018年3月11日まで。
いやいや、短いでしょ。
こう言うアプリは、ユーザー数が増えてこそ、利用価値が高まるんだから、この2ヶ月弱と言う短期間では、ユーザー数だってそんなに増えなさそうだし。
そして、この実証実験に参加しているのは、日本交通グループのタクシーのみ。
それでも300台あるのみたいなので、まぁ、そこそこの台数なのかな…とは思いますが、東京23区と武蔵野市・三鷹市が配車エリアになるとのコト。それだけの広範囲で300台と言うのは、やっぱりちょっと少なさを感じてしまいます。
そして、配車エリアが23区と武蔵野市・三鷹市なので、郊外の“終バス後のタクシー難民”は考慮されていないみたい。
本腰を入れた試験サービスか?と聞かれると、何とも微妙な感じがヒシヒシで、あくまでも“実証実験”レベルなんでしょうかね。
でも、この短期間の実験で、どれだけの試験結果が得られるんだろう…と思っちゃいますけれど、“シェア”と言う新しいサービス概念が、なかなか日本と日本人の間では広まらない中、次に繋がるきっかけになれば良いのですが…
いや、その前にUberとかをしっかり日本に…とは思うけれど。
【関連リンク】
![]() にほんブログ村→他の人の旅ブログも見てみよう!
にほんブログ村→他の人の旅ブログも見てみよう!














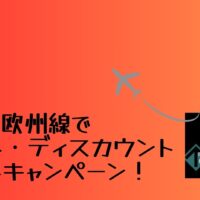
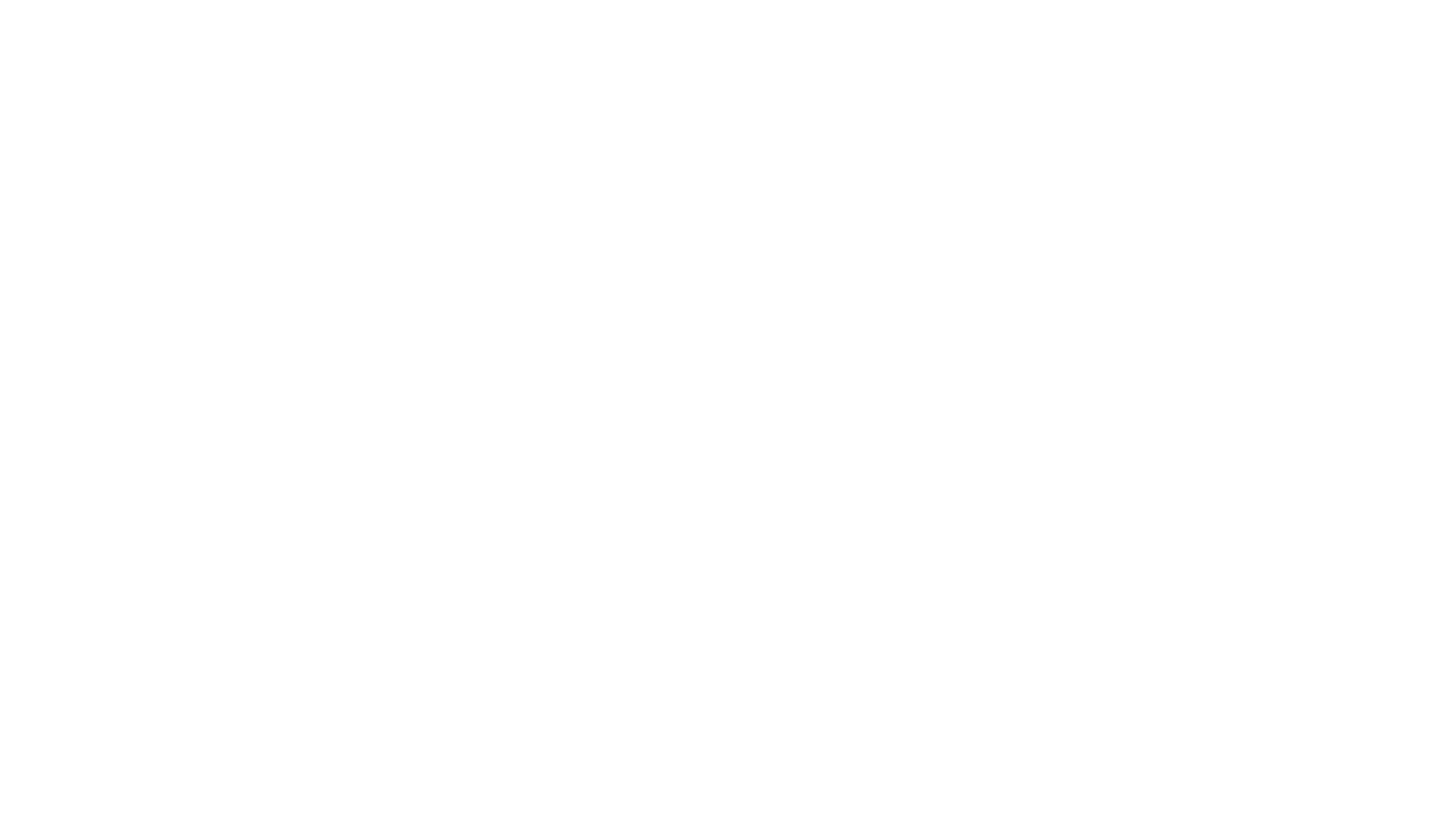

コメントを残す