『バウルの歌を探しに―バングラデシュの喧騒に紛れ込んだ彷徨の記録』
著:川内 有緒
刊:幻冬舎文庫
 |
無形文化遺産の「バウル」
『お前はいったい、何者なのか―』
『それを知ることこそが、人生で一番大切なことだ』
バングラデシュの旅に行くに当たって、スマホにダウンロードして持っていた1冊。
“バウル”。
“ユネスコの無形文化遺産にも登録されている伝統芸能”。
そう言われると、何だかとても体系が確立され、整えられていて、歴史的な何かを感じる訳だけれども、実際の所は、バウル自体、移動をしていて(移動をしないバウルもいるとの話)、どのカーストにも属さず、アンタッチャブルな存在だとも言われているんだとか。
“吟遊詩人”
カッコよく言うと、そう言うのが一番しっくり来る感じがするけれども、実態は、単なる吟遊詩人ではなく、単なる歌い手でもなく、修道者でもあり、解脱者でもあり…
単に“吟遊詩人”と訳してしまうと、ジプシーみたいな感じがしなくもないけれども、生き方・考え方そのものが、“バウル”。
そんな“バウル”を探し求めたバングラデシュの旅の記録が、この1冊。
歌い手、修道者、旅人…バウルが持つ顔
著者2作目となる本書なのだが、そもそも著者をこの本に出会うまで、全く知らないでいた。
いや、読み進めていく中でも、実は男性だとすらしばらく思っていました(著者は女性です)。
しかも、よく分からない“バウル”。
さらに“バウル”自体、歌い手としてのみならず、修道者でもある訳で、読みにくかったらイヤだな…と思いつつ、バングラデシュに到着してからも、しばらく手に取れない1冊だった。

だけれども、ホントに読み進めやすい。
話の進め方とスピードが物凄くイイのが大きいのだろうか。
次から次へと展開されていく物語で、ホントに12日間の旅程なの?と言いたくなるぐらいに、濃く、スピーディーな話の展開。
“バウル”を追い求める話が本筋だけれども、それでいて、風景などの情景描写もしっかりと書き込まれていて、読みながら目を閉じると、バングラデシュの風景・匂いが、瞬く間に目の前に現れてくるぐらい。
途中から、“自分”・“ココロ”と、“自分を探す旅”にも繋がってくるのだけれど、その過程も、若さゆえの自分探しではなく、“自分を取り戻すため”と言う感じがあり、そこにココロを探し、歌うバウルの描写が絡み合ってくる。
きっと歳を重ねて来ると、誰でも1度は考える様な苦悩。
そう言う自己啓発本ではナイから、ココに答えが描かれている訳じゃない。
だけれども、胸をスーッと打つ様な1冊で、アザーンを聴きながら読んでいたら、ジワッと来てしまうぐらいでした。
そう言う意味では、バングラデシュに行く前に読むより、バングラデシュの最中で、喧噪と騒音に紛れながら読んだ方が、より面白い1冊かも知れない。
多分、行く前に読んでいたら、“こんな調子良く、次から次へと話が繋がり、人と会える訳がナイじゃない”なんて思っちゃっていたかも知れないけれど、バングラデシュの最中にいると、何だか全然、あり得そうな話だと思えて来るのも、不思議な感じだけれども。
 |
バングラデシュを読む2冊
旅をする前に読んだ『前へ!前へ!前へ!』。
『前へ!前へ!前へ!ー足立区の落ちこぼれが、バングラデシュで起こした奇跡。』
著:税所 篤快 刊:木楽舎 きっかけは、彼女にフラれたコト。 ただそれだけだった。 そこからバングラデシュの貧しい農村部で予備校事業である「e-Educationプロジェクト」を立ち上げ、大学合格者を出した。 高校3年生が始まる春には、偏差値が28だったと言う著者。 はっきり言って、偏差値28はもう誰にでも出せる数字。 そんな”落ちこぼれ”だった著者が、自身の成長ストーリーを描いた1冊。 …
『前へ!前へ!前へ!』は、著者の若さや行動力が前面に出て来ている本で、それはバングラデシュの持っているエネルギッシュな部分と重なる箇所も多くて面白い1冊だった。
『バウルの歌を探しに バングラデシュの喧噪に紛れ込んだ彷徨の記録 ![]() 』は、それとはまた違って、じんわりと楽しめる1冊でおススメだし、何度か読み返したくなる本。
』は、それとはまた違って、じんわりと楽しめる1冊でおススメだし、何度か読み返したくなる本。
しかも文庫化されているので、手軽に入手出来ると言うのも、嬉しい所ですね。
それにしても…
いつかバウルの歌を、ライブで聴いてみたいなぁ…
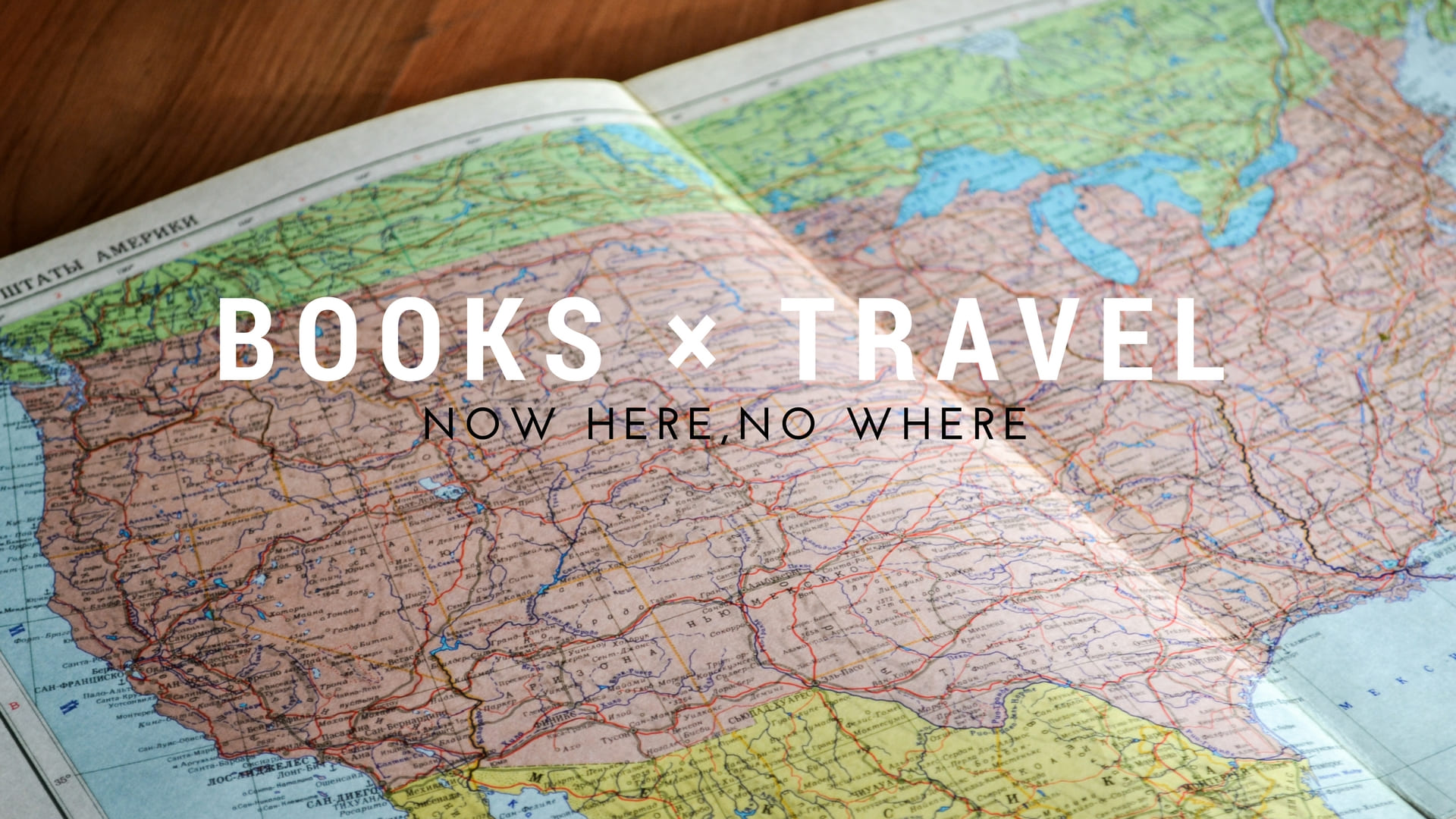
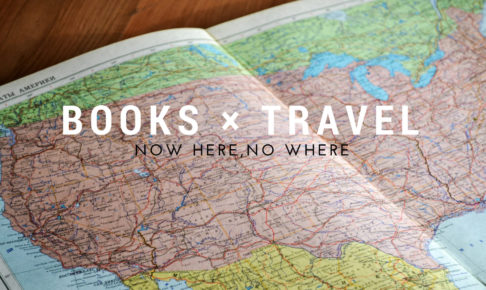
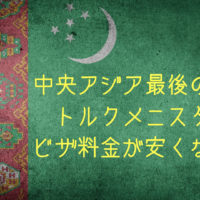






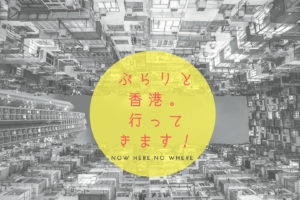




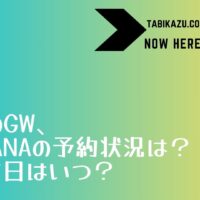

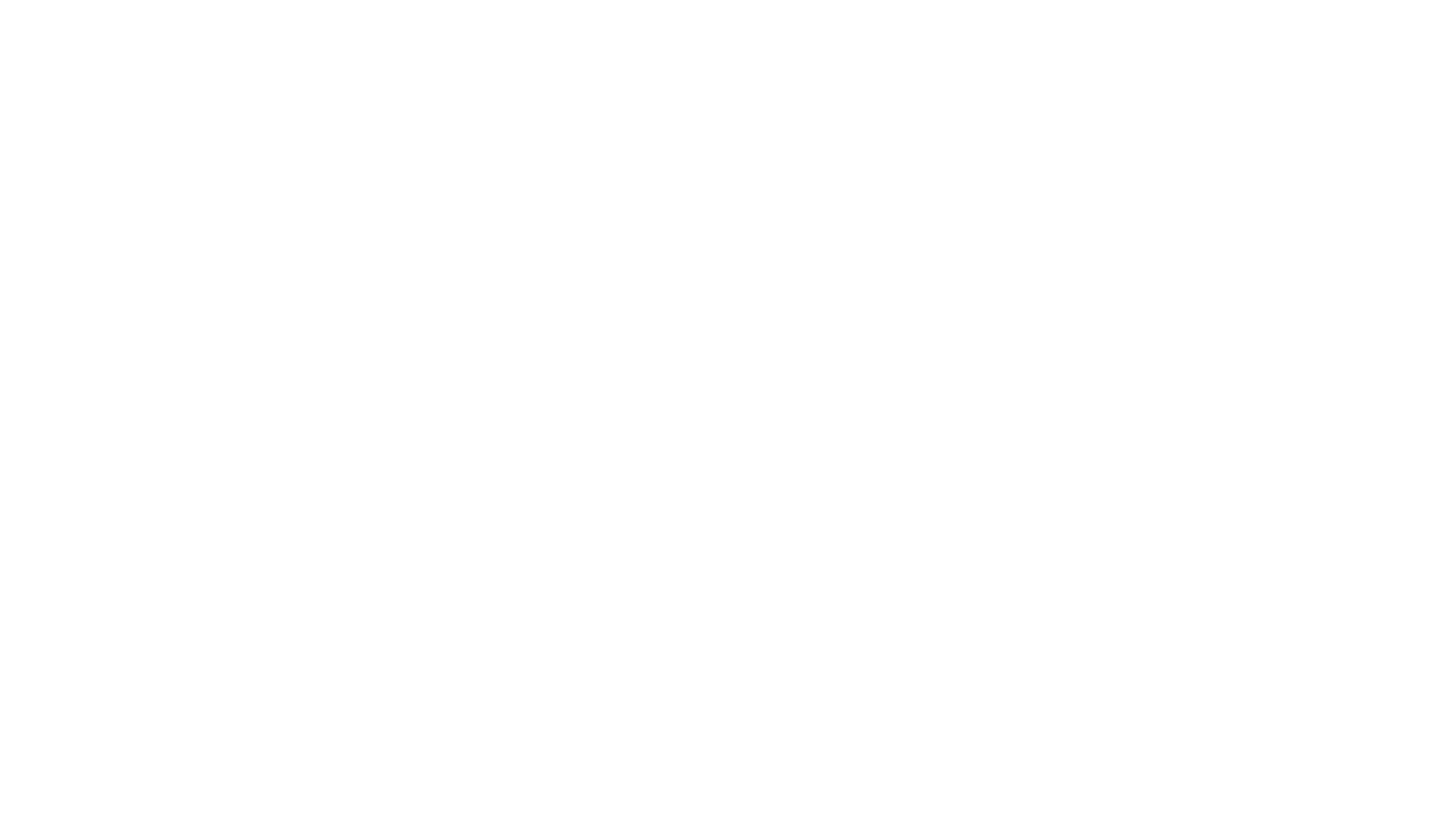

コメントを残す