アメリカとイスラエルと「ユダヤ・パワー」
前回からの続きですが、前回、パレスチナとイスラエルの歴史について振り返ってみたのですが、そもそもどうして、今、わざわざアメリカはエルサレムをイスラエルの首都と認め、大使館を移転しようと思っているのだろう…
そもそもアメリカは元から中立的ではないのは、事実でしょう。
それはアメリカにおけるユダヤ人のチカラと言うのは、計り知れない底力があるのに対して、アメリカにおいてパレスチナにチカラは皆無でしょうから。
人口的に見れば、アメリカ国内におけるユダヤ人の人口は、たかが知れている存在です。
それでも政治を動かす強力な「ユダヤ・ロビー」があるからでしょう。

BruceEmmerling / Pixabay
現在のイスラエルの政策に懐疑的だったオバマ前大統領ですら、この「ユダヤ・ロビー」の中でも最も大きな影響力を持っている「AIPAC」の会合ではイスラエルへの支持を表明していたぐらい。
その「ユダヤ・ロビー」に嫌われるコトを恐れるが故に、アメリカはイスラエルに対して毎年膨大な資金援助を行って来ていましたから。
国連安保理でも、イスラエルの行為を批判する決議に対しては、大方、拒否権を発動して来たのが、アメリカ。
そんなアメリカがイスラエルとパレスチナの間に入った所で、中立な立場でいられる訳がないのですが、それでもアメリカがエルサレムへと大使館を移転すると言うコトを決議したのは、実は最近の話ではなく、それまでの大統領が拒否していただけの話。
何故、今、エルサレム首都認定が出て来たのか
では、何故、今、アメリカはエルサレムをイスラエルの首都に認めようと動き出したのか。
どうして大使館を動かそうとしたのか。
まずは前述の「ユダヤ・ロビー」のチカラもあるでしょう。
そのユダヤ系の支持を集めると言うのも大きな理由にはあるのでしょうが、恐らくは、元々、トランプ大統領は、選挙の時から公約に掲げている話であり、「公約を実行する」と言うアピールにあるのでは…と。

TheDigitalArtist / Pixabay
特にトランプ政権は、公約実行率がそこまで高くはなく、さらに支持率が低迷しているコトもあって、この辺りで「公約を実行する強い大統領」と言うアピールが欲しいのは、間違いがないでしょう。
でも、そのアピールの為に、またしても中東から和平が遠ざかると言うのは、バカな話でしかない。
今も、パレスチナは多くの難民を抱えていると言うのに。
ガザは電力不足が恒久化していると言うのに。
そして、多くの人が困っていると言うのに。
この移転と首都認定では、結局の所、根本は何も解決しないのは、明らかなのに。
★パレスチナ難民については、『ぼくの村は壁で囲まれた―パレスチナに生きる子どもたち』(高橋 真樹・著:現代書館・刊)が分りやすくて読みやすい1冊でした。
このままではダメだと言うのも事実
だけれども、今回のトランプ大統領の決断ですが、思うコトが1つあるのも事実。
それは、「誰もが触らずにいた領域に手を出した」と言うコト。これはトランプ氏だからこその荒業なのかも。
パレスチナ難民が発生しいてから、最早、70年近い年月が過ぎています。
その間、「オスロ合意」など和平に近づいた時期がありましたが、そんな時期は一瞬で、基本的には相交わるコトのナイ状態。

badwanart0 / Pixabay
諸外国からしても、“触らぬ神に祟りなし”ではナイですが、無関心を装う風潮になっていたのも事実でしょう。
何も進展しない中で、パレスチナ難民だけが増え、イスラエルによるパレスチナ侵食だけがじわりじわりと進んでいく様な、そんな状態。
世界の無関心と言うのは、大きなモノで、「IS」に関しての話は遠く日本にも伝わって来るのに、パレスチナ難民であったり、イエメン内戦に関しては、ほとんど日本でもニュースにならない。
そんな状況に、楔を打ったコトだけは間違いがないのでしょう。
勿論、正しい選択だったかと聞かれたら、全然、そうは思えないけれど。
世界各国がもう少し、パレスチナとイスラエルに関わり・関心を持つきっかけにしなければいけないのかも。
単に、アラブ諸国やパレスチナで抗議デモが起きた…と言うだけではなくて。
日本にいるとどうしても「アラブ・イスラム=危ない」と言うステレオタイプの報道が先行するけれども、現在もイスラエルによるパレスチナの実効支配は行われていて、着実に進んでいる。
まずはそこから知らなければならない訳で、アメリカがイスラエル寄りを鮮明にしたからには、もっと国際世論を巻き起こしていくしか、解決方法は無いんだろうと思う訳だし。
日本にいて、出来るコトなんてそんなにナイのかも知れない。
でも、まずは「無関心でいる」コトから1歩、抜け出して、「知る」コトから始めなければ、きっとこの世界は何も変わらないから。
![]() にほんブログ村→他の人の旅ブログも見てみよう!
にほんブログ村→他の人の旅ブログも見てみよう!






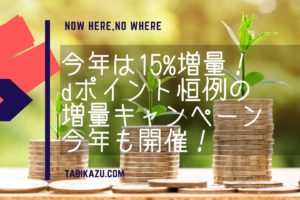
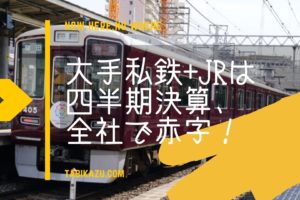
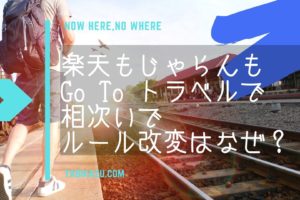




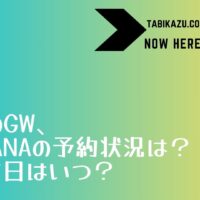

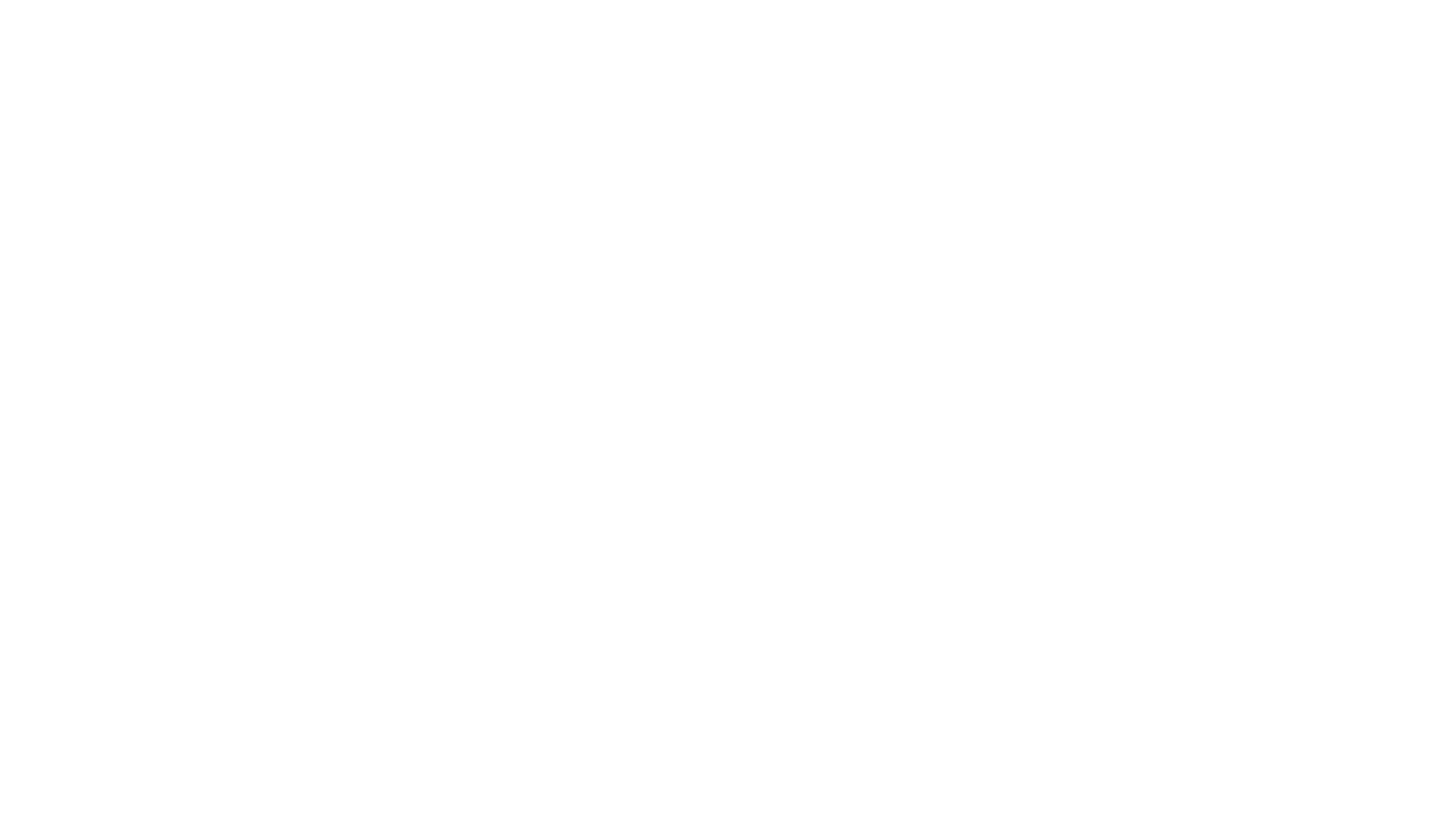

コメントを残す